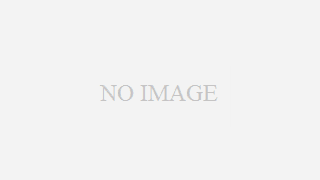瞑想とマインドフルネス瞑想の違い | 瞑想の効果とは?
瞑想は、心を静めて内面に意識を向ける実践全般を指します。
昔から宗教や修行の一環として取り入れられてきましたが、現代ではメンタルケアや自己成長のための習慣として注目されています。
その効果は、科学的にもさまざまな角度から検証されています:
- ストレスの軽減:思考や感情の動きに気づき、適切に手放す力が育つ
- 集中力の向上:注意力や判断力が高まり、仕事や学習のパフォーマンスが向上
- 創造性の促進:視野が広がり、アイデアやインスピレーションが湧きやすくなる
- 感情の安定:自己認識が深まり、心の浮き沈みを俯瞰できるようになる
このように、瞑想は心をフラットに整える習慣として、ストレスや不安のケアだけでなく、創造的な生活の土台にもなります。
瞑想とマインドフルネス瞑想の違い
近年よく聞かれる「マインドフルネス瞑想」。
これも瞑想の一種ですが、目的や意識の向け方が少し異なります。
- 瞑想:静かな時間を持ち、意識を内面に向ける(思考・感情の観察、心の整理)
- マインドフルネス瞑想:今この瞬間に注意を向け、「あるがまま」を評価せずに感じる
どちらも心を整える方法ですが、意識の方向性が違うんです。
2つの瞑想をカメラで例えると…
この違いをイメージしやすくするために、「カメラ」に例えてみましょう。
- 瞑想は、カメラの“フォーカス全体”を調整する作業
→ 自分の心の中、思考の動きにピントを合わせ、整えていく。構図や背景まで意識するような感覚。 - マインドフルネスは、今この瞬間に“シャッターを切る”行為
→ 今目の前にある光や色、動きにフォーカスして、その瞬間をありのままに捉える。
同じ「カメラ(=意識)」を使っても、どこを見ているか、何に注目しているかで体験はまったく変わるのです。
意識の向け方が世界を変える
意識を変えることで、世界の見え方も変わります。
- 普段見過ごしていた景色に美しさを感じたり
- 何気ない日常が、豊かな気づきに満ちていたり
- アイデアが突然浮かぶようになったり
たとえば、芸術作品を見たとき「なんだか懐かしい」「妙に惹かれる」──そんな感覚が生まれるのも、意識の向け方が変わると感じ方が変わるからです。
瞑想とマインドフルネスの違いは、外に向かうか、内に向かうか
私たちは何か物足りなさを感じると、「新しい体験」「刺激」「情報」など外に答えを求めがちです。
でも、瞑想はその逆。
- 瞑想は、自分の内側にある静けさや気づきを深める行為
- マインドフルネスは、自分の外側(今この瞬間)にある体験に目を向ける技法
どちらが正しい、ではありません。
「今の自分にとってどちらが必要か?」を感じながら、場面によって使い分けるのが理想です。
あなたの“意識のカメラ”をどこに向けるか
あなたの手元には、すでに“カメラ”があります。
どんな構図で、どんなタイミングでシャッターを切るか。
それを決めるのは、あなたの“意識”です。
「今の自分は内に向きたいのか、外に意識を広げたいのか」
そうやって自分と対話しながら、瞑想やマインドフルネスを日常に取り入れてみてください。
それだけで、日々の感じ方が少しずつ変わっていくはずです
マインドフルネス瞑想で得られる効果
意識を変えるというのがよくわからないけど、他の事を考えるという事?
A:
もし意識を変えるというイメージが掴みにくい場合は、下記のような錯覚をイメージしてみるといいと思います。

― 見方を変えると、世界が変わる ―
「ルビンの壺(Rubin’s Vase)」とは、一枚の絵の中に“2通りの見え方”が存在する不思議なイラストです。
1915年、デンマークの心理学者エドガー・ルビンによって発表されました。
この絵には、中央に「壺(つぼ)」が描かれているように見える一方で、
両側から向かい合った2人の顔の横顔にも見える――という、**錯視(目の錯覚)**を利用したデザインになっています。
どうしてそんな風に見えるのか?
それは、「どこを背景にして、どこを図(メイン)と見るか」という“脳の選択”によって見え方が変わるからです。
- 中央の白い部分に意識を向けると → 壺
- 両端の黒い部分に意識を向けると → 2人の顔
つまり、絵そのものは一切変わっていないのに、
私たちの「意識の焦点」ひとつで、まったく違うものに見えてしまうのです。
このイラストは、ただの目の錯覚を超えて、
「意識とは、どこに焦点を当てるかで世界の意味が変わる」ということを教えてくれます。
- 同じ状況でも、ある人にはチャンスに見え、ある人には障害に見える
- ある出来事が、希望にも絶望にもなりうる
…それは現実が変わったのではなく、“見え方(意識の向け方)”が変わっただけなのかもしれません。
瞑想では、呼吸や身体感覚、感情に対して「どこに意識を置くか」がとても重要です。
ルビンの壺のように、「視点を変える練習」は、まさに心の見え方を柔軟にするトレーニングになります。
意識の向け方を、自分で意図的にコントロールできるようになると、
日常のさまざまな場面で柔軟な発想や感情の切り替えができるようになります。
たとえば――
- トラブルに直面して精神的に追い込まれていたのに、
→ 視点を変えるだけで、案外シンプルに解決策が見つかることがある - 企画やアイデアがどうしても出てこないときに、
→ 一度意識を外に向け直すと、次々とアイデアが湧き上がってくる - 投資などで損失を抱え、感情的に落ち込んでいたときに、
→ 客観的な視点で損失を見ることで、冷静なリカバリープランを立て直せる - 人間関係で「この人苦手だな」と感じていた相手でも、
→ 合わない部分に注目していた意識を変えることで、共感できる一面が見えてくる - 決断に迷って身動きが取れなかったときに、
→ 一歩引いて見直すことで、自分での解決も、他者への相談も選べるようになる
このように、「意識を向ける方向」を選べるようになると、
物事を一面的に捉えず、柔軟でしなやかな対応力が自然と身についていきます
なぜ「意識すること」が大切なのか?
それは、人間の1日の行動の約95%が“無意識”によって動かされているからです。
たとえば…
- 歩く
- 歯を磨く
- 呼吸する
- スマホをなんとなくスクロールする
こうした日常の動作のほとんどは、自分が意識していないところで自動的に行われています。
脳が意識的に処理できるのは、たった5%ほどとも言われており、
残りの95%は、過去の記憶や習慣、環境に基づいて無意識的に処理されているのです。
実は「自分自身」のことを一番見落としている?
少し質問です:
- あなたの部屋にあるタンスは何段ありますか?
- シーリングファンの羽は何枚?
- 今使っているテレビのメーカーは?
- リモコンの左上にあるボタンの名前、言えますか?
毎日見ているものなのに、意外と答えられなかったのではないでしょうか。
これは、私たちがどれだけ“見ていないものを見ているつもり”になっているかの象徴です。
当然、自分の感情や気持ちについても同じことが起きています。
意識を向けると、無意識の中に“ヒント”がある
- なぜイライラしたのか?
- なぜあの人に嫌悪感を抱くのか?
- なぜ自分は疲れているのか?
- 何を望んでいて、何を恐れているのか?
こうした問いに答えを出すには、“意識を向ける”という習慣が必要です。
マインドフルネスとは、ただ座って無になることではありません。
むしろ、無意識で処理されている「今この瞬間」に、そっと意識を向けてみること。
その中には、自分を整えるヒント、幸せになる糸口がたくさん隠れています。
意識を向けることができるようになると…
- 見落としていた自分の気持ちに気づける
- 無意識の習慣や思い込みから自由になれる
- 選択肢が増え、人生の質が変わってくる
だからこそ、意識の向け方をコントロールできるようになることは、人生を大きく変える力になるのです。
これが、マインドフルネスの本質的な考え方です。